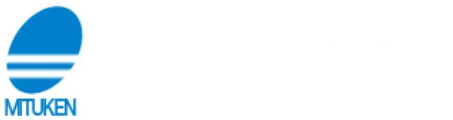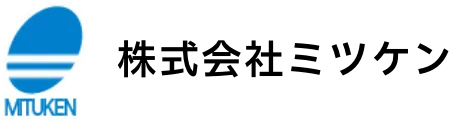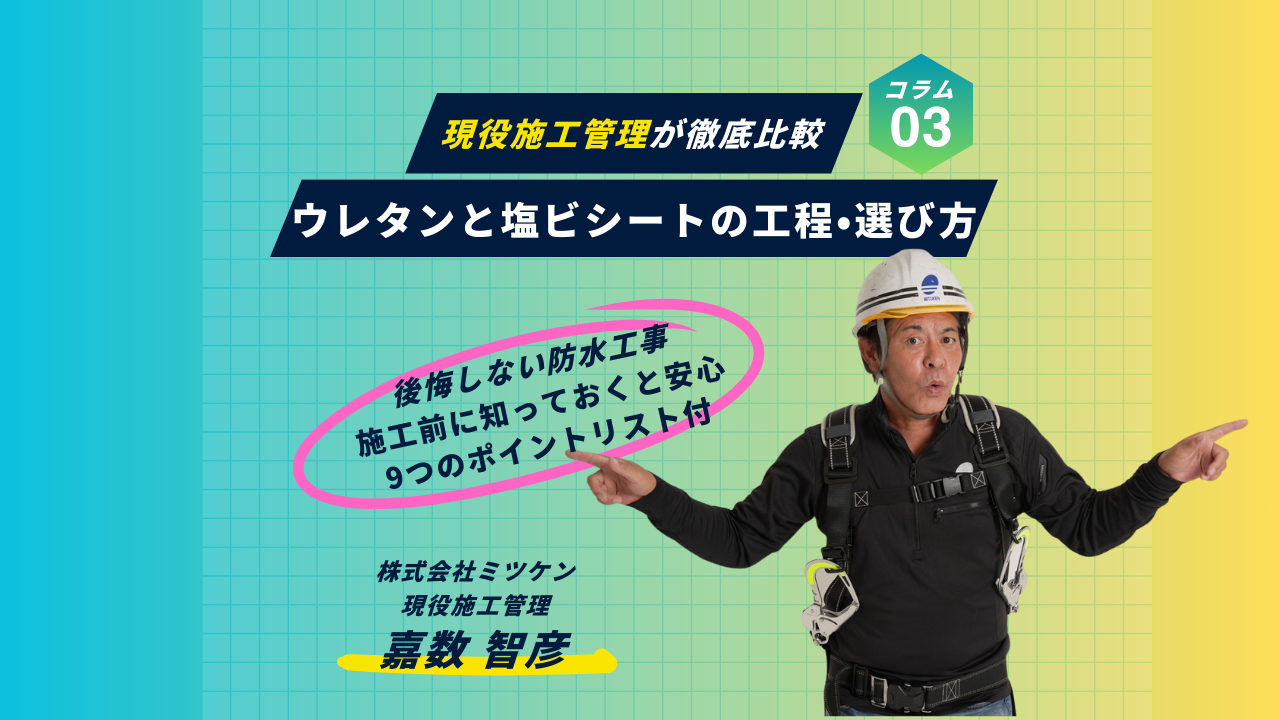目次
対談
ミツケン大家新聞 第5号 アシスト芦屋 新谷有宏代表

海外駐在から家業の不動産業へ——異業種経験で新たな風を吹き込む
谷村:本日はお時間をいただき、ありがとうございます。新谷さんとは、米国不動産経営管理士 CPM® や、CCIMなどを通じて、以前からお話しする機会がありましたが、事業や経営について対面でお話しするのは初めてですね。今日はその点を深掘りしていきたいと思います。まずは、貴社設立の経緯についてお聞かせください。
新谷:1995年にダイヤ商事として親族が創業しました。その後、売買仲介部門を分社し、「ダイヤ不動産販売」としてスタートしました。私の父であり、現在のアシスト芦屋の会長である新谷勝彦が、買取仲介、建売、宅地開発分譲などを手掛けて規模を拡大し、2004年には本社ビルに移転すると同時に社名を「アシスト芦屋」に変更しました。その後、ダイヤ商事が廃業することになったため、業務を引き継いで賃貸・管理部門を設け、今の形になっています。私は2013年にアシスト芦屋に入社し、2020年10月に父が会長に就任したタイミングで代表取締役社長に就任しました。
谷村: 新谷さんは後継者として、大学を卒業後に大手デベロッパーやハウスメーカー、管理会社で経験を積んでから、入社されたのでしょうか。
新谷: いえ、関西学院大学経済学部を卒業後、株式会社ミスミ(東京都千代田区)に入社しました。ミスミは産業用機械部品のメーカーであり、商社機能も持つユニークな一部上場企業です。新規事業の立ち上げや予算編成、業務改革などを行い、その後ドイツに駐在して経験を積みました。国際色豊かな環境下で収益の厳密な管理に関わったことで、ビジネスの基礎を築けたと感じています。その後、経営者としてのキャリアを積みたいという強い思いがあったので、アシスト芦屋に入社しました。

父以外、誰も稼げていなかった——管理会計導入で見えた会社の真実
谷村: 異業種で経験を積んで実家に就かれたのですね。家族経営ならではのプレッシャーや、現場と経営のバランスで悩んだことはなかったですか。不動産業界は、前職の商社とは形態も異なりますし、私自身、防水職人を経て会社を設立したので、創業者と後継者の抱える問題は違う部分が多いと感じています。
新谷: 入社当初、賃貸管理を任されました。しかし、生産性の低い仕事が多く、会社を分析してみると、実際に利益を稼いでいたのは父親だけでした。管理会計を導入してみると、全員が赤字で、誰も自分の分すら稼げていなかったことに気づきました。なんとか管理部を立て直すため、また、私の人件費がさらにかかっている中で、数百万円をセールスフォースに費やしました。しかし誰も活用せず失敗しました。結果として、現場対応の仕事にはログを取る意味がないと判断し、日報をとることも廃止しました。
谷村: 確かに、プロセスが整っていない段階で、管理をしても効果が薄いですから、無駄を省く決断は重要ですね。セールスフォースのような顧客管理ソフトは、プロセスを管理して効率化することで売上げが上がる商品においては有効性がありますが、現場管理には必ずしも適用できないこともありますね。
CPM®の学びが、人事と組織づくりの土台に
新谷: まさにその通りです。試行錯誤の日々が続き、心身ともに負担が大きい時期がありました。そんな中、IREM JAPANが大阪で新たに一期目の講座を立ち上げると知り、心機一転、新たなチャレンジとしてCPM®の取得を決意しました。その頃、実務で自社収益物件の決済に立ち会っていたのですが、バランスシートの変動が激しく、損益計算書の数値だけでは実態を正しく把握できないことを痛感し、最終的にはバランスシートの重要性を強く実感しました。また、不動産は仕入れとして購入すれば商品となり、投資物件として購入すれば固定資産になるため、同じ物件でも財務上の扱いや借入期間が大きく変わります。この仕組みが、CPM®の勉強を通じて整理され、より深く理解できるようになりました。そして、この視点を持っている同期が少ないことに気づき、それが自分の強みだと感じました。
谷村:たしかにBSは大事ですよね。しかし、実は18期も会社経営してきたのに、これまであまり意識していませんでした。今さらですが、その重要性を実感し、数字の見方が大きく変わりました。何が本当に大事なのかが明確になり、経営判断がより的確になったと感じています。
新谷:CPM®は本当に奥が深く、学びの幅が広いので、得られるものは人それぞれなんですよね。そんな時に、父親からこんなことを言われました。「この業界にはいろんな人がいるけれど、信頼できる仲間を作れば大体のことはなんとかなる」と。また実際にCPM®の先輩たちは、「小難しい言い方をやめなさい」「あなたはパッションを持っているんだから、言葉に感情を乗せて伝えなさい」と本音で喝を入れてくれることもあれば、人事評価の仕組みを丁寧に教えてくれることもあり、本当に多くの学びを与えてくれ、『仲間』を得ると同時に、私自身のマネジメントスキルが格段に向上しました。そこから社員と本音で言いたいことをしっかり伝えるようにしたんです。すると次第に社内の雰囲気も変わり、今では社員自ら意見を出してくれるようになりました。振り返れば、受講後、私が最初に実践したのは人事で、今の管理体制を築けたと感じています。
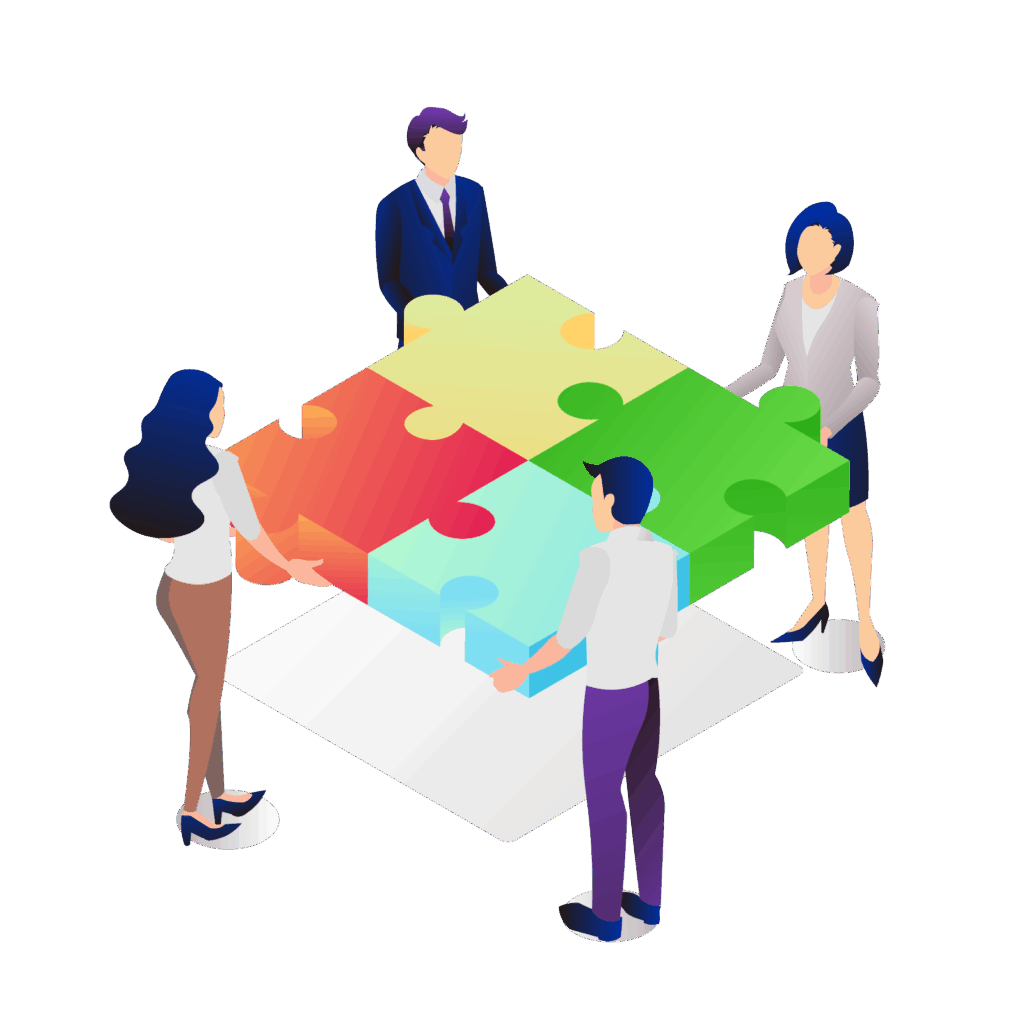
人事こそが会社の核──経営における「人」の重要性
谷村:仕事をするのは結局「人」であり、人事こそが会社の核です。経営を進める中で、つい方法やプロセスに目が行きがちですが、人としての在り方を忘れないことが大事だと感じています。
新谷: 経営者が守るべき最も大事なルールは、従業員とのルールだと思っています。サッカーで言えば、ゴールを決めた選手が「1点」と従業員が自走できる仕組みを作ることです。実務では個別の粗利を1件ごとに計算しており、契約単価に基づく経費には原価として計上すべきものがあります。例えば、賃貸仲介の場合、売上は2カ月後に計上されますが、その1カ月分は業者への広告費です。多くの会社がこれを支払い手数料として処理していますが、正しくは原価として計上すべきです。このような仕組みを導入してから給与や歩合も個人別に可視化することができました。
谷村:財務会計ではなく、管理会計的な視点ですね。当社はまだそこまで踏み込めていません。実は、当社は完全固定給制を採用していますが、最近ではインセンティブも一部導入すべきではないかと考えています。ただ、会社には理念があり、経営の目的があるため、インセンティブ制にすると社員が金銭のほうを重視してしまうのではないかという懸念があり、バランスをどう取るかが課題です。
新谷:適正なインセンティブの比率には基準があり、50%を超えると社員が金銭を最優先する傾向があります。当社では前述の方法で査定を行い、各社員の得意なプレースタイルを見極め、「あなたはこれが得意ですね」と継続的に伝え、意識を持たせることが経営者の役割だと考えています。当社では、個別の成績を経理から社員に直接伝え、さらに社員自身が私に報告する仕組みを取り入れています。これにより、各自が自由に戦略を立てられ、問題などがあればすぐに相談できる環境が整います。一方、事務職に関しては業務を早く終えた分だけ早く帰れる仕組みを導入し、「時間」で評価しています。
谷村:いわゆるティール型組織に近いですね。自由度が高い分、責任も大きくなりますが、社員が主体的に動ける環境が整っているということですね。決定スピードが速くなり、業務の効率が向上しますね。ところで、オーナーとの意思疎通はどのように行っていますか。
新谷:迅速な情報共有のために、LINEワークスを活用しています。たとえば、「水漏れが発生しています」と電話で伝えるよりも、現場の写真を撮って「現在このような状況です」と送る方が、緊急性を正確に伝えやすくなります。
意表をつく修繕提案で、大幅にコスト削減
谷村:さて、「水漏れ」というワードが出たところで、大規模修繕の話に移りたいと思います。今回、当社ミツケンに改修工事をご依頼いただきましたが、その経緯を教えてください。
新谷:まず、RC造の管理物件についてですが、この物件では外壁から水漏れが発生していました。以前、大手企業が高額な金額で修繕をしてくれましたが、水漏れは改善しませんでした。そこで今回、谷村さんに現場調査してもらうと、意表を突く提案を受けたんです。「外壁を直すのではなく、屋根をつけたらどうですか」と。
谷村:調査したところ、雨が吹き抜け部分の内壁に浸透しており、以前の施工に問題があったとは考えにくい状況でした。このため、外壁塗装ではなく、雨の侵入を防ぐ方法を検討しました。吹き抜け側の面は内窓があるため採光の必要もなく、屋根を設置することで根本的に解決できると判断したのです。
新谷:結果として約15万円という低コストで対応できました。従来の修繕なら40〜50万円かかるところだったので、費用対効果も抜群です。オーナーも「目から鱗だ」と大満足でした。ミツケンさんは提案力があり、連絡もスムーズだったので、次は自社所有物件の調査をお願いしました。価格面でも競争力があると感じましたね。


谷村:その次に依頼いただいたのは、築55年、RC造エレベーターなし4階建の物件でした。この物件はかなり老朽化が進んでいて、雨漏りも発生していました。しかも、同じ原因による雨漏りが今後ほかの部屋でも発生する可能性がありました。
新谷:この物件は古い仕様のため、将来的に解体・建て替えをするか、延命修繕を行うかの選択を迫られていましたが、オーナーは延命修繕を選択されました。そこで、貴社に見積書と提案資料を作成してもらい、オーナーに説明したところ、納得いただき「相見積もりは不要です」と即決されました。修繕会社の提案力がいかに重要かを改めて実感しました。我々は単なる施工ではなく、適切な提案を求めているのですが、多くは決められた修繕内容を提示するだけです。
谷村:当該物件は外壁のみならず設備も古く、「家賃を上げる」という戦略が難しいものがありました。工事はオーナーの利益を最大化する手段の一つに過ぎないため、修繕や改修がどれだけ収益につながるのかをしっかり考える必要があります。
利回りだけでは測れない、不動産が支える暮らしと経済
新谷:おっしゃる通り、大規模修繕や建物管理は一度きりのイベントではなく、継続的に発生するものです。建物を修繕するのは、入居者に快適に住んでもらい、家賃をきちんと支払ってもらうため。そう考えると、ただ工事をするのではなく、最適な提案をすることが、本当に大切なんですよね。建物を適切に維持し、入居者の満足度を高めることが、結果的に不動産の価値を守ることにつながります。
谷村:その視点は今後ますます重要になりそうですね。不動産業界全体としても、意識の変化が求められる時代になっていると感じます。新谷さんは、不動産業界の未来についてどのようにお考えですか。
新谷:父が全盛期に活躍していた時代は、人口が増え続け、日本経済も急成長していました。不動産業も右肩上がりの産業だったと思います。しかし、バブル崩壊を経て、不動産は金融商品の一部であるという認識が広まりました。一方で、不動産は単なる金融商品ではなく、人々の住まいや働く場所でもあります。住む人がいなければ家賃は発生せず、オフィスや工場も利用されなければ賃料は生まれません。結果的に、不動産業は経済を支える重要な役割を担っていると感じています。
谷村:たしかに、不動産の購入は、大手企業のみならず、今では一般のサラリーマンなどにも広がっています。投資として語られることが多くなりましたが、本来の役割はそこだけではないですよね。
新谷:だからこそ、この業界に携わる者は誇りを持ち、倫理的に正しい仕事をすることが大切だと考えています。オーナーの資産を管理し、責任をしっかりと自覚することが求められます。「手数料を多く稼ぐ人が偉い」という価値観ではなく、お客様に質の高いサービスを提供できるエージェントが評価されるべきだと思っています。私自身も、そのような業界の在り方を広め、不動産業界の発展に貢献していきたいです。
谷村:倫理観を持って責任ある仕事をすることが、信頼につながることを再認識しました。新谷さんのお話しを聞き、これから自分が関わる業務においても、ただ結果を追い求めるのではなく、誠実で質の高いサービスを提供することを最優先にしていこうと強く決意しました。より良い未来を作り出すために邁進していきたいと思います。本日は貴重なお話をありがとうございました。
この記事をシェアする
プロフィール

アシスト芦屋 新谷有宏代表
芦屋市出身。1981年生まれ。
大学卒業後、機械部品通販商社の株式会社ミスミに入社し、予算編成や業務改革を行う。ドイツ駐在を経て、父親が代表を務める株式会社アシスト芦屋に転職する。2022年10月、父親の会長就任に伴い、代表取締役社長に就任する。
2025年6月よりIREM JAPAN会長就任予定。保有資格は、CPM®・CCIM、他資格多数。2020年度CCIM JAPAN会長。現 IREM JAPAN理事、KG リアルターズクラブ幹事、芦屋市商工会青年部

ミツケン 谷村充功代表
八尾市出身、富田林市育ちの1977年2月生まれ。一男二女の大黒柱。
株式会社ミツケンの代表を務め、木造3棟、区分1室の家主としても活動している。
保有資格は、二級建築士、一級施工管理技士、CPM、CCIM
所属する大家の会:元気が出る大家の会、CGS、PIC、がんばる大家の会、ドリーム家主倶楽部、不動産経営研究会ほか